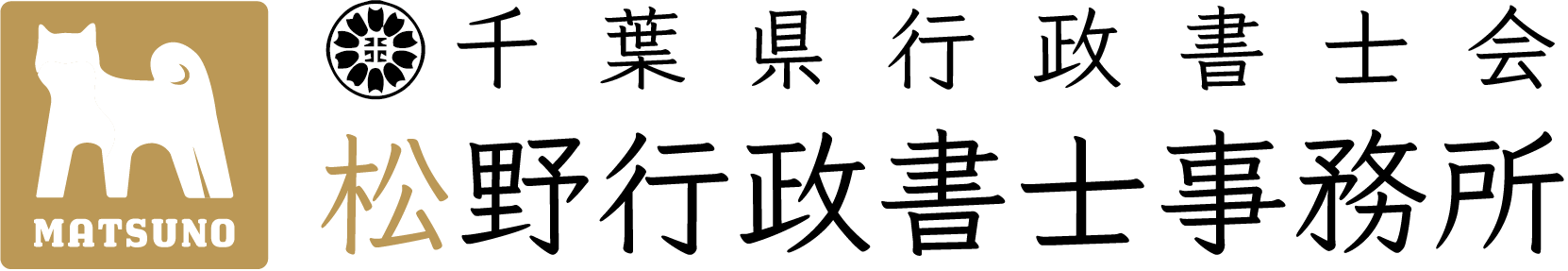目次
「もう融資は受けられない」と思っていませんか?
「創業から数年経って、もう制度融資は使えないし、借入も限界かもしれない」
「金融機関と取引はあるけど、いつも保証人がネックになる」
これは、実際に市川市内の中小企業の経営者から聞いた言葉です。
業績が安定していても、資金調達の相談となると急に慎重になってしまう方が少なくありません。
理由の一つが、“経営者保証”という壁。
金融機関からの借入にあたって、経営者が個人で保証人となる制度──
それが「経営者保証」です。
創業時には仕方なく受け入れていたこの仕組みが、のちに資金調達の選択肢を狭め、事業承継にもブレーキをかけてしまうのです。
「これ以上リスクを背負いたくない」
「次の世代に保証人という負担を背負わせたくない」
そんな思いを抱える経営者が増えている一方で、「保証を外す」という発想自体がまだ広まっていません。
けれど実は、一定の条件を満たせば“経営者保証を解除できる”制度が整ってきています。
しかもこれが、「新たな融資の可能性を開く鍵」にもなっているのです。
「借りられるのに、相談できない」──資金調達の現場で何が起きているか
「本当は、もう少し運転資金に余裕がほしい。でも…」
「金融機関に行くのが億劫で、つい後回しにしてしまった」
「保証人の話が出た時点で、あきらめた」
市川市内やその周辺で事業を営む中小企業や個人事業主の方々から、こうした声をしばしば耳にします。
実際、業績が好調な企業でも、資金調達の「最初の一歩」を踏み出せずにいるケースは少なくありません。
その背景には、以下のような“相談しづらさ”が潜んでいます。
「経営者保証」という“見えないハードル
多くの中小企業にとって、金融機関との融資交渉で最初にぶつかる壁が「経営者保証」です。
創業時には当然のように求められ、なんとなくそのまま継続しているという方も多いのではないでしょうか。
しかし、事業が軌道に乗ってきた今、「自宅や個人財産を担保にしてまで…」という心理的負担が重くのしかかります。
とくに次のようなケースでは、経営者保証の存在がボディーブローのように効いてきます。
- 個人保証のリスクが重くのしかかり、新規借入に踏み切れない
- 子どもに事業を継がせたいが、「保証人にはなりたくない」と拒まれてしまう
- 金融機関との関係が「保証を前提」に固定化してしまっている
「制度を知らなかった」が命取りになるケースも
ある市川市内の飲食業の事業者は、コロナ禍での資金繰りに悩んでいたものの、「どうせ借りられないだろう」と思い込み、相談を後回しにしてしまいました。
ところが、実はその企業には無担保・無保証で受けられる制度融資の枠があり、
タイミングさえ合えば十分に活用できたはずだったのです。
最終的に別ルートで短期資金を確保しましたが、条件は決して良くありませんでした。
資金調達=借金、という誤解
もう一つ根深いのが、「資金調達は“借金”であり、できるだけ避けたい」という考え方です。
たしかに無駄な借入は避けるべきですが、計画的な資金調達は、むしろ経営の武器になります。
とくに、経営者保証を外したうえでの借入であれば、“個人リスクなしで資金を手元に残す”ことも不可能ではないのです。
このように、資金調達の現場では「制度を知らない」「保証が怖い」「相談のタイミングを逃す」
という理由で、本来使えるはずの選択肢を自ら手放している事例が後を絶ちません。
そこで次章では、そもそも「経営者保証とは何か?」をあらためて整理しつつ、どうすれば解除できるのか、その基本的な考え方と制度の動きをご紹介します。
「経営者保証って、外せるの?」──制度の基本と解除の3要件
「経営者保証の解除? そんなことできるんですか?」
実際に、これまで多くの経営者がこう驚かれてきました。
ですが今、一定の条件を満たすことで、金融機関との契約から“保証人”を外すことが可能になってきています。
それを支えるのが、金融庁と全国銀行協会が策定した
「経営者保証に関するガイドライン(平成26年策定)」というルールです。
そもそも「経営者保証」ってなに?
たとえばあなたの会社が、銀行から1,000万円を借りたとします。
このとき、法人として借りるだけでなく、経営者個人も保証人になる──
これが「経営者保証」です。
つまり、万が一会社が返済不能になった場合、あなたの“個人財産”で返す義務があるということ。
自宅や預金、最悪の場合は自己破産も……といった事態につながる重大なリスクです。
「じゃあ、どうすれば外せるの?」──3つの解除要件
保証を外すには、以下の3つの条件を満たしているかどうかがポイントです。
1.法人と経営者の「資産・経理の分離」ができているか
→ 法人のお金と個人のお金がきちんと分けられ、経理処理が明瞭であること
→ 例:法人名義の通帳を経費に使い、個人と混同していない
2.法人の「財務状況」が一定の健全性を保っているか
→ 返済能力があり、黒字経営またはそれに準じた状況であること
→ 資産超過(債務よりも資産が多い状態)などが目安
3.金融機関への「情報提供」が適切に行われているか
→ 決算書、試算表、事業計画書などの資料を、定期的に提出しているかどうか
→ 信頼関係の構築が鍵になる
この3つを満たしていれば、保証を求めない融資(=無保証融資)を受けられる可能性が高まります。
“ガイドラインの存在”を知らないと、話が始まらない
実はこの「経営者保証ガイドライン」は、あくまで“努力義務”です。
つまり、銀行から「保証を外しますよ」と言ってくれることはほとんどありません。
だからこそ、経営者側がこの制度の存在を知り、
「当社は要件を満たしていると思うのですが、保証解除のご相談は可能でしょうか?」
とこちらから”働きかけることが重要です。
経営者保証を外すために、まずやるべき3つの準備
「経営者保証を外せるなら、うちも検討したい」
そう思っても、何から手をつけていいのか分からない方も多いはず。
そこでここでは、中小企業が今すぐ始められる3つの準備をご紹介します。
【準備①】“個人と会社のお金”を分けるところから
まずは、「会社と経営者の財布を分ける」ことがスタートラインです。
たとえば──
- 個人名義の通帳を経費に使っていませんか?
- プライベートな支出を会社のカードで払っていませんか?
こうした曖昧さは、金融機関に「この会社は管理が甘い」と判断されてしまいます。
✅ 法人名義の通帳・カードを整備し、経費処理を明確にする
✅ 代表者貸付金・借入金の整理や見直しを行う
こうした“見える化”が、保証解除に向けた土台づくりになります。
【準備②】金融機関との信頼関係を「資料」で築く
「決算書さえ出しておけばOK」と思っていませんか?
保証を外すには、過去の業績だけでなく“将来の経営計画”を見せることが重要です。
✅ 月次試算表の提出で経営の見える化
✅ 売上の見通し、経費計画を含む事業計画書の作成
✅ 補助金申請・新規取引先の情報も共有
「この会社は、信頼できる」「継続的な関係を築きたい」
そう思ってもらえるような資料提出が、保証解除の後押しになります。
【準備③】専門家に“保証解除の前提条件”を診断してもらう
自社の状況が「解除要件を満たしているかどうか」は、なかなか自分では判断しづらいもの。
✅ そこでおすすめなのが、専門家による事前のチェックです。
たとえば行政書士や中小企業診断士など、経営改善や資金調達に詳しい専門家に現状を診てもらえば、「何を整えれば保証解除に近づけるか」が明確になります。
商工会議所や金融機関との連携支援もありますし、地域密着で動く専門家も多く存在します。
「誰に相談すればいいか分からない」という方は、そこからの情報収集も有効です。
「保証を外す」ことから始まる、資金調達と事業の未来
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
もしかすると、これまで資金調達といえば「借金は怖い」「保証人は仕方ない」──
そんなふうに考えていたかもしれません。
けれど今、時代は変わりつつあります。
経営者が個人保証という重荷を手放し、もっと自由に、もっと戦略的に資金調達を行う。
そんな流れが、静かに、しかし着実に広がっています。
保証解除が「融資の選択肢」を広げる
保証が外れることで、金融機関との関係も変わります。
- 新たな事業展開のための資金調達がしやすくなる
- 後継者が承継を前向きに考えられるようになる
- 個人リスクに縛られず、柔軟な意思決定が可能になる
これは単なる“借入の話”ではありません。
経営者としての自由と、次世代への橋渡しを実現する手段です。
まずは、「話をしてみる」ことから
もちろん、すべての企業がすぐに保証解除できるわけではありません。
でも、「うちでも可能性あるかもしれない」と気づくことが、最初の一歩です。
その一歩を、信頼できる相談相手と一緒に踏み出せば、資金調達の可能性は大きく広がります。経営に真摯に向き合う事業者がこうした制度を活用し、事業承継や成長への道を切り拓いています。
「経営者保証を外せる未来」に向けて
私はこれまで、市川市で資金調達や補助金申請をご支援するなかで、多くの経営者の決断と向き合ってきました。
行政書士として、制度のしくみや書類作成はもちろん、「経営者の本音に寄り添う支援」が何よりも大切だと感じています。
「これは自分のことかもしれない」
そう思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。
保証を外すという選択が、事業の未来を変えるきっかけになるかもしれません。