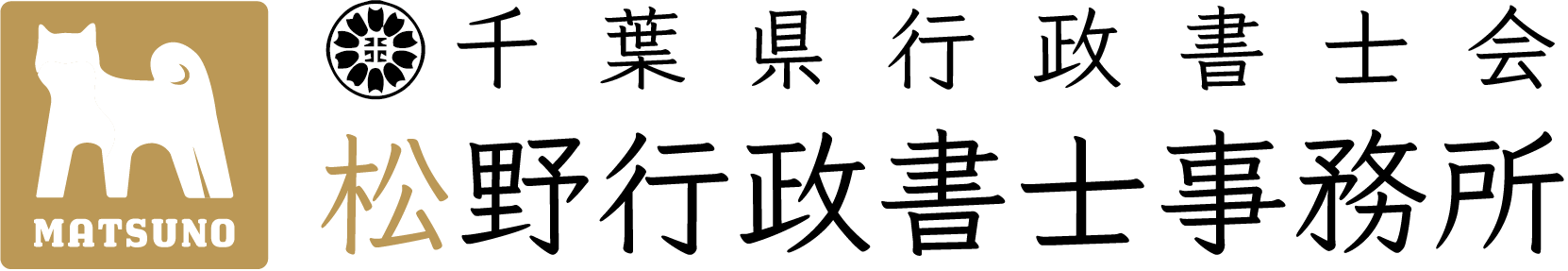目次
なぜ今「事業承継・M&A補助金」なのか
経営資源の引継ぎは「待ったなし」の課題に
近年、市川市をはじめとする首都圏の中小企業では、経営者の高齢化と後継者不足が大きな経営課題となっています。
中小企業庁の調査によれば、後継者不在率は全国で60%を超えており、地域によっては70%近くに達するケースもあります。市川市・船橋市・松戸市といったベッドタウン型の商圏では、個人事業主・小規模事業者が多いため、この問題はより身近なものといえるでしょう。
これまで、「事業承継」や「M&A(企業の合併・買収)」は一部の大企業や成長企業の話と思われがちでした。
しかし、後継者不足が進行する中小企業においても、事業を引き継ぐ・譲る・統合するという選択肢は極めて現実的なものとなっています。
承継の壁は「想い」ではなく「お金」
「後継ぎがいない」「従業員に引き継ぎたいが資金が足りない」
──こうした声は、市川市の中小事業者からもよく聞かれます。
実際、事業承継やM&Aには 設備投資・改修費・仲介費用・専門家費用・廃業費用など、さまざまな資金負担が発生します。
後継者の意志があっても、資金面のハードルが高く承継を断念するケースは少なくありません。
この「資金の壁」を突破するために設計されたのが、今回ご紹介する
👉 「事業承継・M&A補助金」 です。
補助金は“単なる資金援助”ではない
この補助金は、事業承継・M&Aを戦略的に進めるための実行支援ツールです。
たとえば次のような場面で活用が可能です。
- 設備の老朽化対策や事務所の改築
- M&A仲介やデューデリジェンス(DD)などの専門家活用
- M&A後の経営統合(PMI)への投資
- 廃業に伴うコスト負担と再チャレンジの準備
承継・M&Aは、単なる経営の「終わり」ではなく、次のフェーズに進むための「転換点」です。
この補助金を上手に活用することで、資金面の不安を軽減しながら、企業の存続と成長を両立することができます。
タイミングを逃さず活用することが鍵
2025年度の十三次公募では、申請期間が 10月31日(金)〜11月28日(金)17:00(予定) と限られています。GビズIDの取得にも時間を要するため、関心のある企業は早期準備が必須です。
地域経済を支える市川市の中小企業にとって、この補助金は「今こそ使うべき制度」といえるでしょう。
次章では、この補助金がどのような枠組みで設計されているのかを、わかりやすく整理していきます。
補助金の4つの枠組みと対象者を理解する
自社の「状況」に合わせて補助枠を選ぶことが重要
事業承継・M&A補助金は、単一の補助金ではありません。
企業が 「いつ」「どの段階で」「どのような形で」 事業承継・M&Aに取り組むかによって、利用できる枠組みが変わります。
大きく分けると、以下の4つの枠があります👇
| 枠名 | 内容 | 上限額 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| ①事業承継促進枠 | 設備投資・店舗改築など | 最大1,000万円 | 親族・従業員承継予定者 |
| ②専門家活用枠 | M&A仲介・DD・FA費用 | 最大2,000万円 | M&Aの売手・買手 |
| ③PMI推進枠 | 経営統合・設備投資 | 最大1,000万円 | M&A後の統合段階 |
| ④廃業・再チャレンジ枠 | 廃業費用・再挑戦準備 | 最大150万円(加算可) | 廃業+再スタート予定者 |
この4つの枠を理解し、自社の現状と照らし合わせることで、無理のない申請と採択率の向上が期待できます。
① 事業承継促進枠・設備投資で未来を描く
親族や従業員に事業を引き継ぐ場合に活用できる枠です。
例えば、市川市内で長年営業してきた町工場や建設会社などが、承継をきっかけに老朽化した設備を入れ替えるケースが典型です。
- 補助対象
設備投資費用、店舗・事務所の改築工事費用 など - 補助率
1/2(小規模事業者は2/3) - 上限額
800万円(賃上げ実施で最大1,000万円)
✅ ポイント
後継者が決まっている事業承継では、設備更新や事業拡張を補助金で後押しできるため、承継後の経営安定に直結します。
② 専門家活用枠・M&Aの“見えないコスト”を補助
M&Aを行う際に負担となるのが、仲介・FA費用、デューデリジェンス(DD)、セカンド・オピニオンなどの専門家コストです。
この枠では、その費用の一部を補助します。
- 補助対象
FA・仲介費用、DD費用、表明保証保険料 など - 補助率
1/3〜2/3(条件により変動) - 上限額
最大2,000万円
✅ ポイント
M&A支援機関に登録された仲介業者やFAが対象です。
「買収側」「売却側」いずれでも申請可能で、専門家との連携を強化できるメリットがあります。
③ PMI推進枠・統合フェーズの“地味だけど重要”な投資を支える
M&Aの成立はゴールではなく、むしろスタートです。
この枠では、統合(PMI=Post Merger Integration)にかかる費用を補助します。
- 補助対象
設備費、外注費、委託費、専門家活用費 など - 補助率
1/2(小規模事業者は2/3) - 上限額
800万円〜1,000万円(専門家活用類型は150万円)
✅ ポイント
M&A後の混乱を防ぎ、事業を軌道に乗せるための「統合期」こそ、資金が必要です。
業務システムの整理や生産ラインの統合などに活用できます。
④ 廃業・再チャレンジ枠・次の一歩を踏み出すために
「廃業」という言葉にはネガティブなイメージがありますが、近年では事業を一度整理して、新たなチャレンジをする経営者も増えています。
この枠は、そうした再出発を支援する制度です。
- 補助対象
廃業支援費、在庫廃棄費、解体費 など - 補助率
1/2または2/3 - 上限額
150万円(他枠と併用可能)
✅ ポイント
廃業を前提としながらも、他の補助枠と併用できるのが特徴です。
たとえば廃業と同時にM&Aや新事業を立ち上げるケースにも対応しています。
状況に応じて「複数枠の併用」も可能
たとえば、
- 設備投資(①)+M&A仲介費用(②)
- PMI統合投資(③)+廃業費用(④)
このように、複数枠を組み合わせて申請することで、承継から再出発まで一気通貫の支援を受けることも可能です。
「今の自社はどのステージにあるのか」を正確に把握することが、最初の一歩です。
次章では、こうした枠組みが 実際にどんな場面で使えるのか──
👉 具体的なケースを想定しながら「補助金活用のシナリオ」を紹介します。
補助金を活用できる主なケース
「制度を知っている」だけでは成果につながらない
事業承継・M&A補助金は、内容が複雑に見えるため「うちには関係ない」と感じてしまう経営者も少なくありません。
しかし、制度を「自社の状況」に置き換えると、意外なほど多くのケースで活用できることが分かります。
ここでは、市川市・船橋市・松戸市などの中小企業で想定される活用事例を紹介します👇
ケース① 【親族・従業員承継】
設備更新を補助金でまかなう
- 業種
製造業(町工場) - 所在地
市川市 - 状況
創業40年の金属加工業。社長が70歳を迎え、長男への事業承継を予定。 - 課題
老朽化した設備の更新と工場内のレイアウト変更に多額の資金が必要。
👉 活用できる補助枠:①事業承継促進枠
- 設備投資や工場改修費用の最大1,000万円まで補助可能。
- 承継と同時に最新設備への更新を行い、生産性アップも実現できる。
✅ ポイント
後継者が決まっている場合は、採択可能性が比較的高い枠です。
ケース② 【M&A活用】
専門家費用を抑えて買収・売却を進める
- 業種
建設業 - 所在地
船橋市 - 状況
代表者が後継者不在。第三者承継(M&A)による売却を検討中。 - 課題
M&A仲介・FA費用、デューデリジェンス(DD)のコストが高額。
👉 活用できる補助枠:②専門家活用枠
- M&A仲介・FA費用など最大2,000万円まで補助対象。
- 中小企業庁が登録するM&A支援機関経由の費用が対象となる。
✅ ポイント
売手・買手いずれも対象。M&Aを円滑に進めるための実務的支援を受けやすい枠です。
ケース③ 【M&A後の統合】
PMI(統合)コストを補助金でカバー
- 業種
運送業 - 所在地
松戸市 - 状況
同業他社をM&Aで買収。システムや営業体制の統合が必要。 - 課題
統合作業に伴うコンサル料やシステム移行コストが経営を圧迫。
👉 活用できる補助枠:③PMI推進枠
- 設備費・外注費・専門家活用費などに最大1,000万円の補助。
- PMI(統合プロセス)に必要な投資をサポート。
✅ ポイント
M&Aの「後」にフォーカスした数少ない補助金。統合に失敗するとM&A自体が失敗になるため、このフェーズでの活用は極めて有効です。
ケース④ 【廃業と再スタート】
廃業コストを補助金で軽減
- 業種
小売業 - 所在地
市川市 - 状況
長年営んだ店舗を閉じ、オンライン事業に転換予定。 - 課題
在庫廃棄・内装解体・撤去にコストがかかる。
👉 活用できる補助枠:④廃業・再チャレンジ枠
- 廃業支援費・解体費など150万円を上限に補助。
- 他枠と併用することで、新事業への移行コストを抑制できる。
✅ ポイント
「廃業=終わり」ではなく「次の挑戦」を後押しするための枠組みです。
ケース⑤ 【複数枠の組み合わせ】
承継+投資+統合を一気に進める
- 業種
サービス業 - 所在地
市川市 - 状況
後継者承継を進めながら、新拠点立ち上げとM&Aによる事業拡大を計画。 - 課題
複数の投資・コストを一度に捻出するのは難しい。
👉 活用できる補助枠:①+②+③の併用
- 承継時の設備投資、M&A仲介費、統合コストを段階的に補助。
- 承継〜拡大フェーズを戦略的に進められる。
✅ ポイント
補助金を“単発”ではなく“中長期戦略”として組み込むことで、資金負担を大幅に軽減できます。
「どの枠が自社に合うか」を見極めることが成功の鍵
補助金の制度を正しく理解し、自社の課題と照らし合わせることで、活用の幅は大きく広がります。
事業承継を“先送り”するのではなく、“補助金を活用して今動く”ことが、将来の事業基盤を守る一歩です。
次章では、実際の申請で つまずきやすいポイント と、スムーズに進めるための 実務上の注意点 を解説します。
申請の実務・JグランツとGビズIDの注意点
「知っている」と「申請できる」は別問題
補助金の制度を理解しても、いざ申請となると
「やり方が分からない」「申請システムが難しそう」と感じる経営者は少なくありません。
特に今回の 事業承継・M&A補助金は「電子申請限定」。
申請書を紙で提出することはできません。
そのため、申請準備には通常の補助金以上の「事前段取り力」が問われます。
GビズIDプライムの取得は“最初の関門”
申請の第一歩となるのが、GビズIDプライムの取得です。
これは、経済産業省が運営する電子申請システム「Jグランツ」を使うための共通IDで、法人・個人事業主ともに必須です。
- 📌 取得には通常 2〜3週間程度 かかる
- 📌 本人確認書類(印鑑証明書など)が必要
- 📌 郵送による手続きが必要(オンライン完結ではない)
👉 つまり、申請書類を作り始める前に、GビズIDの申請を早めに行うことが非常に重要です。
締切間際に取得を試みると、申請そのものが間に合わない可能性もあります。
Jグランツの基本操作と申請の流れ
Jグランツは補助金の電子申請システムで、申請者自身がアカウントを使ってオンライン申請を行います。
操作に慣れていない方でも、流れを理解しておけばスムーズに進めることが可能です👇
Jグランツ申請の基本ステップ
- GビズIDを取得
- 事業承継・M&A補助金の申請ページにアクセス
- アカウントでログイン
- 必要情報(企業情報・事業計画・経費内訳など)を入力
- 添付書類(見積書、計画書、決算書類など)をアップロード
- 申請内容を確認し、電子送信
✅ ポイント
書類の不備があると差し戻され、再提出に時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。行政書士や中小企業診断士などの専門家にサポートを依頼する企業も増えています。
申請期間とスケジュール感を把握する
今回の十三次公募は以下の期間で募集されています👇
- 申請受付期間
2025年10月31日(金)〜11月28日(金)17:00(予定)
この1か月の間に、GビズIDの取得、事業計画の作成、見積書・根拠資料の準備、申請入力・送信──といった作業を終える必要があります。
申請の混雑やシステムトラブルが起きやすいのは、締切直前です。
最終週に申請するのはリスクが高いため、11月中旬までに提出できるスケジュールを意識しましょう。
実務上のつまずきポイントと対策
| よくあるつまずき | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| GビズIDの遅れ | 申請開始が遅れる | 早期申請(締切1か月前には取得) |
| 書類不備 | 決算書・見積書・事業計画の不足 | 専門家チェックまたは早期準備 |
| システム操作 | Jグランツの入力に不慣れ | 事前にテスト申請やログイン確認 |
| 計画の曖昧さ | 採択率が低下 | 投資目的・承継内容を明確に記載 |
早めの準備が「採択率」に直結する
補助金の申請は「計画書の完成度」で採択結果が大きく変わります。
特に本補助金は承継・M&Aという性質上、経営戦略との整合性が重要視される傾向があります。
- 目的が明確
- 経費の根拠が具体的
- 承継やM&Aの流れが整理されている
こうした計画書を整えるためには、早期に準備を始めることが何よりの対策です。
市川市・周辺の事業者こそ「早めの一歩」を
市川市・船橋市・松戸市などの中小企業は、少人数で事業を運営しているケースも多く、日々の業務で手一杯になりがちです。
だからこそ、「時間との勝負」になる補助金申請では、余裕を持った行動が採択率を高める最大の武器になります。
地元企業が補助金を“戦略的に”活かすために
補助金は「受け取る」だけでなく「活かす」ことが重要
補助金は、申請が通れば資金がもらえる便利な制度──
そう思われがちですが、本当の価値は「お金」そのものではなく、それをどう使うかにあります。
事業承継・M&A補助金は、単なる資金支援ではなく
👉 企業の転換点を後押しする“レバレッジ資金” です。
- 設備投資を“延命”ではなく“次世代対応”へ
- M&Aを“防衛策”ではなく“成長戦略”へ
- 廃業を“撤退”ではなく“再挑戦”へ
つまり、補助金を経営戦略のなかに位置づけることで、経営の選択肢が広がるのです。
設備投資 × 承継で、事業の「若返り」を
市川市・船橋市には、長年地域を支えてきた製造業・建設業・運送業の中小企業が多くあります。
こうした企業が直面しているのは、老朽化した設備と高齢化した経営体制です。
例えば、承継を機に
- 新しい機械設備を導入する
- 事務所や工場をリニューアルする
- DX(デジタル化)への投資を行う
といった取り組みを補助金で支援すれば、“守りの承継”ではなく“攻めの承継”に変えることができます。
✅ 後継者が次の時代に合わせて事業を拡大できるよう、補助金を「未来への先行投資」として使うのがポイントです。
M&A × 専門家活用で、成長を加速する
第三者承継(M&A)は、後継者不在の企業だけでなく、「事業拡大」を目指す企業にも有効な手段です。
専門家費用を補助金でカバーできれば、中小企業でもM&Aに取り組みやすくなります。
- 仲介・FA費用の補助
- デューデリジェンス(DD)費用の補助
- PMI(統合)コストの補助
これにより、たとえば地元の建設会社が近隣の同業者を引き継ぎ、エリア拡大・規模拡大を図る──といった攻めの展開も可能です。
✅ これまで「費用の壁」で諦めていたM&Aが、実現しやすくなります。
PMI × 組織強化で、“統合の失敗”を防ぐ
M&Aで最も失敗が起こりやすいのが、「統合(PMI)」の段階です。
この補助金では、統合フェーズに必要な費用(専門家活用・設備統合・システム移行など)も対象になります。
- 営業拠点の一本化
- 生産・配送ラインの統合
- 経理・人事・システムの統一
これらを補助金で支援することで、統合リスクを抑え、事業をより早く軌道に乗せることができます。
✅ M&Aは“買って終わり”ではなく、“統合して成果を出す”ことが重要です。
廃業 × 再チャレンジで、「攻めの撤退」を
「廃業」という言葉には後ろ向きな印象がありますが、実は経営戦略の一つです。
撤退にかかるコストを補助金で軽減できれば、次のチャレンジに資金とエネルギーを集中させられます。
- 不採算事業の整理
- 余剰設備・在庫の処分
- 解体・撤去費用の補助
✅ 廃業は失敗ではなく「リスタート」。
この枠をうまく活用すれば、経営資源を再配置して次の成長ステージに進むことが可能です。
専門家と組むことで、補助金を“戦略ツール”に変える
補助金は、単独で申請・活用するよりも、
👉 行政書士・税理士・中小企業診断士・金融機関などの 専門家と連携することで成果が大きく変わります。
- 採択率の向上
- 計画書のブラッシュアップ
- 投資戦略の整理
- 金融機関との連携による追加資金調達
市川市のような地域密着型の経済圏では、地元の士業や金融機関との連携ネットワークをうまく使うことで、申請から実行までスムーズに進めることができます。
補助金を「未来の一歩」に変える
- ✅ 補助金は“もらう”だけでなく“活かす”ことで真価を発揮する
- ✅ 設備投資・M&A・統合・再チャレンジ…自社の戦略に合う枠を選ぶ
- ✅ 早期準備と専門家連携で、採択率と活用効果を高める
補助金は、経営者にとって「守りの資金」ではなく、「未来への先行投資」を実現するための武器です。
市川市・近隣地域の中小企業にとって、このチャンスをどう活かすかが、次の10年を左右します。